内閣府は2020年1月に「量子技術イノベーション戦略」を策定し、量子コンピューターや量子通信、量子センシングといった基礎技術の開発を推進している。またこれらの技術を支えるために、人材育成、国際連携、知的財産の管理、標準化に向けた取り組みも行われている。さらに2025年5月には、既存の量子技術に関する政府戦略を強化・補完する目的で「量子エコシステム構築に向けた推進方策」が報告された。このように量子技術の社会実装と産業化に向けた取り組みは加速しており、注目度が高まっている。こうした背景から、今回は量子技術の理解を深めるための書籍を紹介する。
量子情報科学
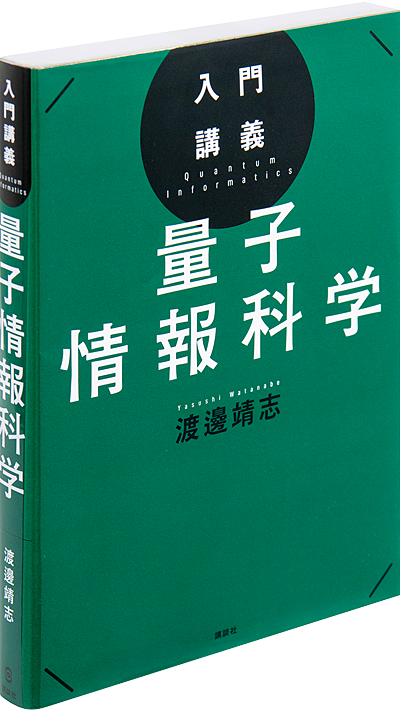
3,850円(税込)
講談社サイエンティフィク
本書は、量子情報科学分野の急速な発展を受けて急務となっている、人材育成の一助となることを目的に執筆された一冊だ。「とにかく分かりやすく」をモットーに、既存の量子情報科学書の「翻訳」を志している。例えば、文献によって表記ゆれが目立つ専門用語や記号(notation)は、標準的と思われるものに統一。また、小見出しを多用することで、読者が「今、何について議論しているのか」を把握しやすくする工夫も施されている。本書は13の章と五つの付録から構成されている。第1章は、量子ビットでは0と1の状態を同時に取れる「重ね合わせの原理」を持つといった量子の不思議な性質を概観。その後、量子力学と情報科学の進展を辿り、両者が融合して生まれた量子情報科学がもたらす、量子コンピューター・量子通信・量子暗号の発展について考察する。第2〜5章では量子計算、第6〜10章では量子通信、第11章では暗号通信、第12章では量子誤り訂正符号と、量子情報科学に関わる基礎を網羅的に学ぶことが可能だ。そして第13章では、量子コンピューターと量子暗号通信の現状と今後の展望をまとめている。読者がつまずきやすいポイントには例題を配置しており、理解を深める助けとなってくれる。量子情報科学を初めて学ぶ読者にとって、確かな道しるべとなる。
量子超越
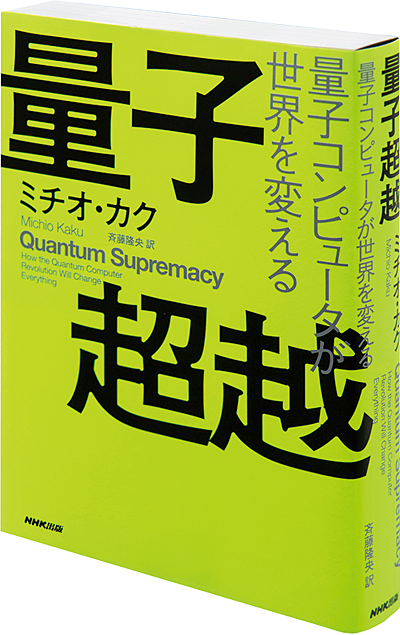
2,860円(税込)
NHK出版
本書は大きく分けて二つのパートで構成されている。第1部では、世界最古のアナログコンピューターと呼ばれる、天体の動きを予測するための歯車式の計算機「アンティキティラ島の機械」から始まり、現代の量子コンピューターに至るまでの歴史を紹介している。第2部では、量子コンピューターが将来的に実現する可能性があるさまざまな技術や事象を、具体的かつ網羅的に取り上げている。例えば、第8章では肥料製造技術の改善について触れており、第10〜13章にかけては創薬や遺伝子編集など、医療分野への応用が詳細に述べられている。本書は、量子コンピューターが社会にもたらすインパクトを知るための一助となるだろう。
AI・量子コンピュータに
かかわるリスク管理
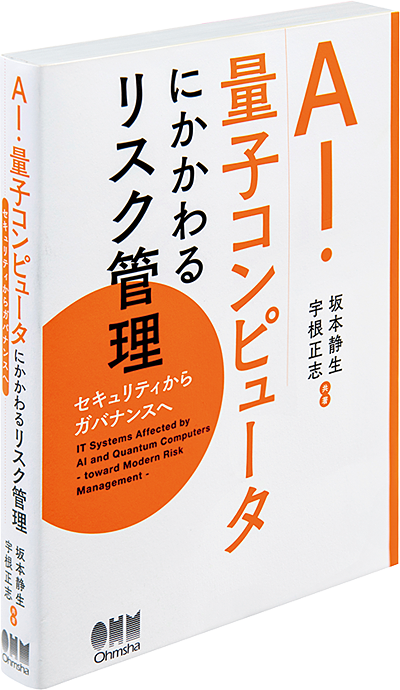
4,840円(税込)
オーム社
本書は量子コンピューターとAIがもたらすリスクに対して、組織がどう向き合い、管理していくべきかを解説している。第1章では具体的なリスクを紹介。例えば、量子コンピューターによって公開鍵暗号が解読され、第三者に情報が漏えいする可能性や、AIによるプライバシー侵害といったリスクを挙げる。こうしたリスクへの対処方法について、米国国立標準技術研究所(NIST)のリスク管理フレームワーク「Risk Management Framework for Information Systems and Organizations」(NIST Special Publication 800-37 Revision 2)に基づき、体系的に説明している。さらに、金融業界における具体的な取り組みも紹介しており、量子技術とAIの時代におけるリスク管理の実践的な指針を提供する一冊だ。


