IT活用が企業の成長や変革に貢献する一方で、企業が使用するIT製品が増加し、それに伴う使用済みIT資産への対応が課題となっている。特に2025年はWindows 10のサポート終了や第2期 GIGAスクール構想となる「NEXT GIGA」に伴い大量のPCがリプレースされた。これらのPCも数年後には次のリプレース時期を迎える。その際大量の使用済みPCに、どのように対応すべきか、適正な処分とリユース・リサイクルへの取り組みについて考えたい。
E-wasteがリサイクルの5倍の速度で増加
リサイクル率60%で収益化が可能と指摘
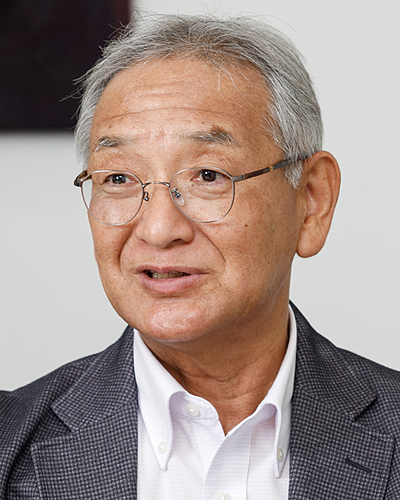
代表理事
デジタルリユース
代表取締役社長
及川信之 氏
国連のグローバル電子廃棄物モニターが公表した報告書「グローバル電子廃棄物モニター 2024」(2024年11月2日版)ではE-wasteはリサイクルされている量の5倍のスピードで増加していると指摘している。
同報告書では2022年に過去最高の6,200万トンのE-wasteが発生し、2010年から82%、すなわちほぼ倍増しているという。さらに世界中でE-wasteの年間発生量は年間260万トン増加しており、2030年までに2022年比で33%増の8,200万トンに達すると予測している。
増加するE-wasteに対してリサイクル率は2022年が22.3%であったのに対して、2030年までに20%に低下すると指摘している。E-wasteの排出量がリサイクルされる量の5倍の速度で増加するという指摘から、今後E-wasteの問題は世界で深刻化することが容易に想像できる。
E-wasteのリサイクルが進まない要因として製品のリユースや部品などのリサイクルに伴う処理のコスト負担が大きく、利益を得られないことが挙げられる。この見解に対してグローバル電子廃棄物モニターは「各国が2030年までに電子廃棄物の収集とリサイクル率を60%にできれば、人間の健康リスクを最小限に抑えるなど、コストを380億米ドル以上上回る利益が得られる」と強調している。
※出所:国連 グローバル電子廃棄物モニター(https://ewastemonitor.info/the-global-e-waste-monitor-2024/
使用済みIT資産の廃棄に伴う
情報漏えいのリスクは随所に

副代表理事
アセットアソシエイツ
代表取締役
伊藤修司 氏
E-wasteにはさまざまな電気電子機器が含まれるが、中でも世界で今後さらに活用が拡大するIT製品の占める割合が大きいと考えられる。IT製品をリユース・リサイクルする場合、PCやサーバー、ストレージ、ネットワーク機器などのIT資産には個人情報や企業の機密情報など重要なデータが残されている可能性がある。
そのため企業がIT資産を廃棄する際は、データを適切に消去することはもちろん、環境保全に向けた機器のリユース・リサイクルに取り組むことが求められる。その際に企業が対応しなければならないのが「ITAD(アイタッド)」と呼ばれる取り組みだ。
ITADとはIT Asset Dispositionの略語で、「IT資産を適正に処分する」という意味だ。PCやサーバー、ネットワーク機器、そしてスマートフォンなど企業がビジネスで利用しているIT資産では、日々個人情報を含む重要なデータを扱っている。これらIT資産を廃棄する際に機器に残されたデータが外部に流出すると、サイバー攻撃による情報漏えいと同様に深刻な打撃を受けることになる。
IT資産を処分する際の機器からの情報漏えいのリスクは、処分を依頼した業者が機器を引き取り、輸送、保管の際にデータが残った機器が盗難に遭うことや、不十分な消去作業によるデータの残留など、ユーザー企業の手を離れた後の方が大きい。そこでITADに準じたIT資産の適正処分が必須となる。
ただしITADには特定の法令はなく、IT資産の廃棄に関わる複数の関連法令に基づいて適切に実施する必要がある。具体的には「個人情報の保護に関する法律」や「廃棄物処理法」、そして「資源有効利用促進法」や「不正アクセス禁止法」などが挙げられる。IT資産を保有するユーザー企業はIT資産を廃棄する際にこれらの法令を遵守するコンプライアンスが求められる。では具体的にどのような対応をすべきなのか。
「ITAD」に準じた対応により
使用済みIT資産をビジネス化
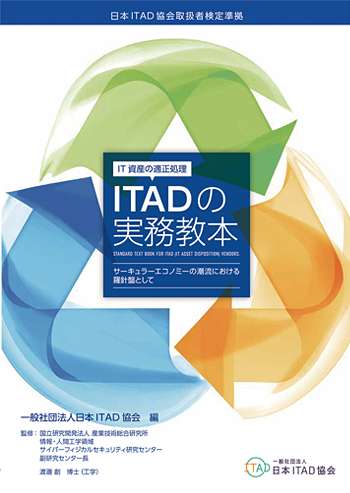
IT資産を廃棄あるいはリユース・リサイクルする際に、データ消去はどのツールを使うのか、データ消去したことをどう証明するのか、IT資産の廃棄およびリユース・リサイクルを請け負う業者はどのように選定すべきなのかなど、ITADに対応するには多くの要素を満たす必要があるが、法令には具体的な方法が示されていない。
そこで日本ITAD協会がITADに対応するためのガイドラインを策定してガイドブック「ITADの実務教本」を発行するとともに、ITADを適正に取り扱っている事業者に「ITAD認定事業者資格」を付与している。
また日本ITAD協会はITADに関する取り扱いに専門性を有し、IT資産の撤去、運搬、保管、データ抹消、再生、再資源化処理(リユース・リサイクル)、廃棄といった一連の処理を行っている取扱事業者およびその関連事業者が、関係する我が国の法令の学習、コンプライアンスや実務面での理解度を向上・確認することを第一の目的に「ITAD取扱者検定試験」を実施している。
日本ITAD協会 代表理事でデジタルリユースの代表取締役社長を務める及川信之氏は「当協会では良質なリユースPCの普及および適切なリサイクルの拡大に向けて、PCのストレージ内のデータを適切に抹消するためのガイドラインや、スマートフォンのデータやオンサイトデータに関してのガイドラインを策定し、それぞれに使用するデータ抹消ソフトウェアについては製品検証を実施した上で、当該ソフトウェアについて『データ抹消ソフトウェア資格認定』を付与しています」と説明する。
また同協会の副代表理事でアセットアソシエイツの代表取締役を務める伊藤修司氏は「PCやサーバー、ストレージのほかに、ネットワーク機器にも設定情報が記録されており、適切なデータ抹消・初期化作業が不可欠です」と指摘する。
ITADへの対応は情報漏えいの防止や環境保全への貢献に加えて、使用済みIT資産のビジネス化にもつながる。及川氏は「使用済みIT資産を再販売する際、例えばPCではOSやアプリケーションのライセンスを不正に利用されるなどの損害が発生する恐れがあります。ITADに準じて処理したIT資産ならば、使用済みのIT資産を安全かつ適法に取り扱え、市場を健全化することでビジネスの拡大が期待できます」と説明する。
さらに伊藤氏は「IT資産を販売している企業にITAD事業者資格認定を取得していただくことで、回収からデータ抹消、再生、リユース販売、リサイクル、廃棄までビジネスを拡大できます。またこの一連のプロセスに関して、当協会の会員を紹介することもしています」とアピールする。



