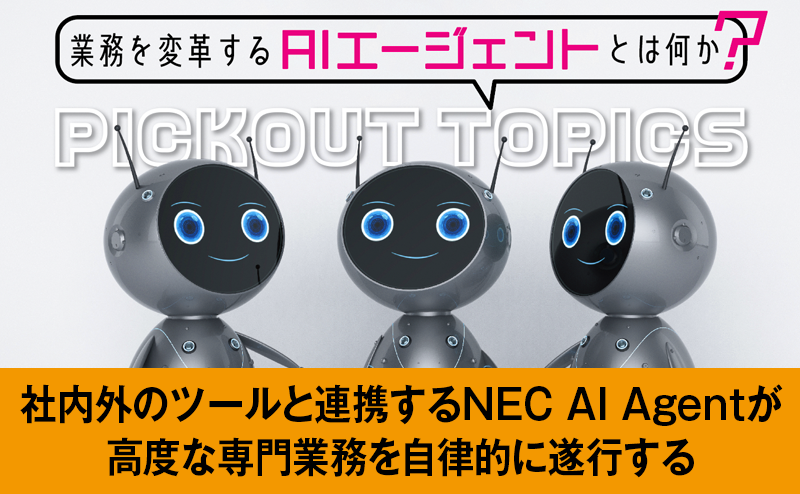NECは、国内ベンダーとしていち早くLLM(大規模言語モデル)「cotomi」を開発するなど、AI関連ビジネスに積極的に取り組んできました。現在、同社が注力しているのが、高度な専門業務の自動化を目指すAIエージェント「NEC AI Agent」です。その特長と、NECが描くAIビジネスの最前線を紹介しましょう。
国産LLMをベースにした信頼性

石川和也 氏
NECでは顧客の業務変革を実現するため、AIサービスの提供を推進しており、その中で自社で開発したLLMのcotomiと、AIエージェントであるNEC AI Agentを提供している。「cotomiは2023年8月から提供をスタートしました。国内大手メーカーの中では一番に近いスピード感で国産LLMをリリースできたと自負しています」と振り返るのは、NEC AIビジネス・ストラテジー統括部 エバンジェリストの石川和也氏。このcotomiは高速で高い日本語性能を持ち、オンプレミス型やクラウド型、ハイブリッド型など、ユーザー企業の求めるセキュリティ要件に応じた導入が可能だ。国産LLMである安心感から、自治体での導入事例もある。
このcotomiのLLMを用いたAIエージェントとして提供をスタートしたのがNEC AI Agentだ。NECのAIエージェントはユーザーが依頼したい業務を入力すると、AIが自律的にタスクを分解して必要な業務プロセスを設計し、それぞれのタスクに最も適したAIやITサービスを選択して業務を自動的に実行してくれる。第一弾として、経営計画や人材管理、マーケティング戦略など、社内外の情報を包括的に検索し、意思決定が求められる業務のプロセスを自動化するNEC AI Agentを2025年1月から提供している。
石川氏は「従来のLLMは、業務プロセスにおいては1タスクだけを支援する位置付けであり、経営課題から見た効果が出にくい側面がありました。AIエージェントはLLMと違い、業務プロセス全般を認識した上で指示を出すと、業務プロセスを遂行するためのタスク分解をし、それぞれのタスクをこなすために必要な情報を自律的に取りに行きます。当社の生成AI事業はBtoB向けのビジネスですので、分解されたタスクに対して社内外の情報にアクセスしたり、必要なシステムを動かしたりすることを有機的に判断して実装していく存在として、NEC AI Agentを開発しました」と語る。
社内外のデータを自律的に調査

NEC AI Agentの活用例として石川氏は、協同商事 コエドブルワリー(以下、コエドブルワリー)との取り組みを挙げた。コエドブルワリーは、埼玉県川越市発のクラフトビールブランドだ。世代を超えたコミュニケーションを増やすため、NEC AI Agentとビール職人が協働して20〜50代といった各世代の特徴や価値観を分析し、味や香りなどで表現した4種のクラフトビール「人生醸造craft」を開発したという。
石川氏は「このシステムアーキテクチャには、ベースにcotomiがあります。例えばビール職人が『20代日本人をイメージして、社内外のレシピ情報を参考に、新しいクラフトビールのレシピを作成して』とプロンプトを入力すると、その指示を受けたNEC AI Agentがタスクを分解し、割り振りを行います。今回のプロンプトでは20代日本人と書かれているため、まず20代の特徴や価値観を検索してペルソナを作成します。次に社内外のレシピ情報を検索し、その情報を基にレシピ案を作成して職人に共有するというプロセスを、全て自律的に行います。構造的には、業務プロセスを定義し、それをさまざまなタスクに分解して、問い合わせや要約、計算などを自由度高く自律的に実行する仕組みです」と語る。
社内外のデータを検索する場合の検索先なども自律的に判断する。例えば社内のレシピデータに加え、Googleなどのサーチエンジンを活用して世界中のオープンデータからレシピ情報を検索する。NEC AI AgentはAIエージェントが外部ツールにアクセスするための共通プロトコル「MCP」(Model Context Protocol)や、AIエージェント同士を連携させる共通プロトコル「A2A」(Agent2Agent)などに対応させ、これらをサポートしている外部サービスであれば問題なく連携できる環境を目指すという。「今後MCPに対応するサービスは増加することが見込まれていますので、できることはさらに増えていくでしょう」と石川氏は指摘する。
一方で、自律的にタスクを実行するからこそ、その出力結果に人間側が納得できないこともあるだろう。石川氏は「NEC AI Agentでは、戻ってきた回答に改善の余地を感じる場合、そのタスク自体を再定義することが可能です。現時点では、全ての業務や新たな企画に対して完全に自動的にできるわけではないので、足りない部分は人間の手でプロセスを追記したり編集したりすることも必要です」と語る。
このNEC AI Agentは前述した通り、2025年1月から順次機能をリリースしており、すでに数多くの導入実績があるという。「NECは、自社が最初の顧客であることを意味する『クライアントゼロ』という考え方の下、自分たちをゼロ番目の顧客として製品やサービスを使用しています。そして、その活用経験を基にNEC AI Agentの提案を進めています」と石川氏は語る。

マルチモーダル対応も進める
AIサービスの提案先の業種としては主に製造、金融、自治体、医療といった4業種だ。これらの業種はもともとNECがSIerとして実績があるため、多くの業務ノウハウが蓄積されている。例えば生成AIの導入事例として、製造業の企業で活用されているPLM(製品ライフサイクル管理)システムにcotomiを実装し、使いやすいUXの実現や技能伝承の要約、法規制変更への対応などを行ったこともあるという。
一方でこれらの業種では、秘匿性の高い情報を数多く取り扱うとともに、ハルシネーションなど生成AI活用におけるリスク対策もより強固に求められる。
石川氏は「2025年3月26日に、当社はシスコシステムズと、日本企業や自治体のさらなる生成AI活用の推進を目指し、AIガバナンス分野での協業をスタートしました。本取り組みの一つとして、NECのコンサルティングサービスとシスコシステムズが提供するAIセキュリティソリューション『Cisco AI Defense』を組み合わせたNECのAIガバナンスサービスを、金融・製造業や公共機関、自治体を中心としたお客さまに向けて、2025年秋から提供開始する予定です。Cisco AI DefenseはAIの開発や展開、使用に伴うリスクに対応するために設計されており、業界標準に沿った生成AIの活用が可能になります。また当社は2019年に『AIと人権に関するポリシー』を策定して以来、AIガバナンス基本規定やAIリスク管理マニュアルなどを整備し、実際の運用を通じてAIリスクを低減してきました。これらの経験を基にしたコンサルティングサービスと、シスコシステムズのテクノロジーの両輪でお客さまのAI活用をサポートしていきます」と語る。
実業務へのAIエージェント活用を進める上では、さまざまなAIやツールを活用する必要がある。NECは音声認識、映像解析、画像解析などのAI基盤を有しており、それらとLLMを組み合わせることで、例えば映像を基にそのリスクを判定するような事柄に活用するなど、業務の幅を広げることが可能だ。これらをAIエージェントで自律的に連携させることで、より高度な専門業務の自動化にも寄与できる。「今後は前述した高度な専門業務の自動化に加え、AIガバナンスとセキュリティの面で『信頼できるAI』を作り、スピーディーな社会実装を目指します。NECでは現在、当社の先進的なテクノロジーとビジネス変革の知見・経験を体系化した価値創造モデル“BluStellar”を掲げており、お客さまの経営課題を伴走型で解決することを目指しています。このキーテクノロジーに据えているのがAIとセキュリティであり、BluStellarの概念の下、市場に対してさらなる価値提供を進めていきます」と石川氏は展望を語った。