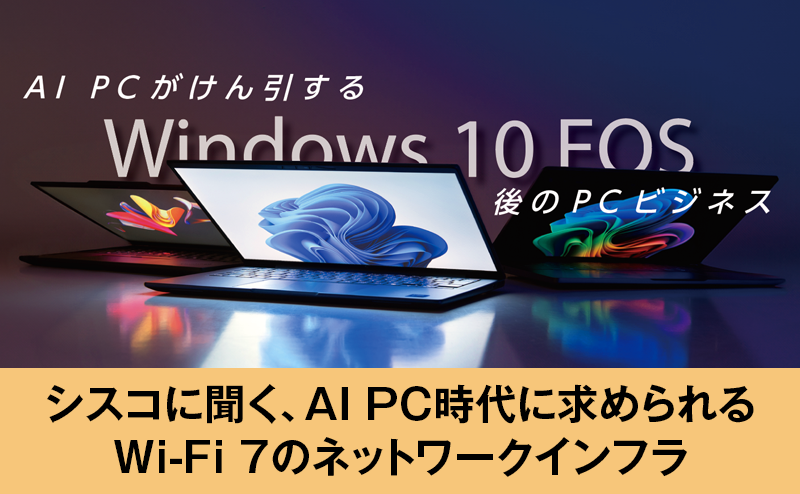2023年末に日本国内での利用が解禁されたWi-Fi 7。Wi-Fi 6(6E)をベースにしつつ、最大通信速度や接続の安定性が大きく向上している。2024年11月ごろからはWi-Fi 7対応モデルが各ネットワークベンダーからリリースされ、急速な勢いで導入が進んでいるという。そしてCopilot+ PCをはじめとしたAI PCの存在が、このWi-Fi 7対応アクセスポイントの普及を、さらに後押しする可能性がある。エンタープライズネットワーク市場におけるトップランナーとして、Wi-Fi 7対応アクセスポイントを展開するシスコシステムズに、同規格の優位性と、AI PC普及によって起こる市場の変化を聞いた。
導入が加速するWi-Fi 7
その市場の背景と動向
IT専門調査会社のIDC Japanが2024年7月2日に発表した「国内企業向けネットワーク機器市場予測」によると、2025年から2026年にかけてWi-Fi 7対応製品のラインアップが拡充され、ハイエンドアクセスポイントを中心に市場への導入が進み、予測期間の後半にかけて既存のWi-Fi環境からWi-Fi 7への置き換えが徐々に進むことが見込まれている。シスコシステムズ 執行役員 ネットワーキング事業担当 高橋 敦氏もその言葉を裏付けるように「Wi-Fi 7の導入が急速な勢いで進んでいます」と指摘する。
背景の一つとして挙げられたのが、Wi-Fi 5対応製品のEOSだ。2016〜2019年ごろにかけて広く普及したWi-Fi 5対応製品のEOSが進みつつあり、そうした既存環境からのリプレース先としてWi-Fi 7対応製品を選択するケースが増加傾向にある。「当社が展開するネットワーク製品は、ほぼWi-Fi 7対応にシフトしています。エンドポイント側はまだWi-Fi 7に未対応のものもありますが、今後はWi-Fi 7への対応がスタンダードになるため、ネットワークインフラの環境を先に整備しておくことは大きなメリットとなるでしょう」と高橋氏は指摘する。
シスコシステムズでは、こうしたWi-Fi 7対応のアクセスポイントとして、エンタープライズ向けの「Cisco Wireless 9178」シリーズ、「Cisco Wireless 9176」シリーズを2024年11月12日にリリースしたほか、同じくWi-Fi 7対応アクセスポイントとしてよりコンパクトでさまざまな業種の企業が導入しやすいエントリーモデル「Cisco Wireless 9172」シリーズを、2025年春から市場に投入している。多様なモデルのアクセスポイントをラインアップすることで、顧客の要望に柔軟に対応できるようにしているのだ。
Wi-Fi 7規格は、冒頭に述べた通り最大通信速度や接続の安定性が向上した、パフォーマンスの高い通信規格だ。Wi-Fi 6(6E)の最大帯域幅は160MHz幅だったが、Wi-Fi 7では320MHz幅と倍になっている。これまでボトルネックになりやすかったアップリンクのパフォーマンスも大幅に向上しており、特にリアルタイム通信で高い効果を発揮する。このリアルタイム通信に対するメリットは、Copilot+ PCをはじめとしたAI PCの利用が増える今後のビジネスシーンにおいても大きな効果を発揮する。
シスコシステムズのWi-Fi 7対応アクセスポイント



トランザクションが増えるAI PCに
求められるネットワーク性能と管理
シスコシステムズ ネットワーキング事業 プリンシパルソリューションズエンジニア 生田和正氏は「Windows 10のEOSに伴うリプレース先の端末として、多くのPCメーカーがAIを売りにしたPC端末を提案しています。しかしAIは、ネットワークの帯域に求める要件がシビアです」と指摘する。
例えばLLM(大規模言語モデル)に質問を投げかけてその回答を返してもらうやりとりには、小さなトランザクションが数多く発生するという。また、生成AIを活用し、同時通訳を行う機能を搭載したデバイスは、音声入力に対してリアルタイムでAI処理を行う必要があるが、この処理にも多くのトランザクションが発生する。ネットワークの帯域によってこの処理が遅れるとユーザーにとってのストレス要因になり得る。
生田氏は「AI PC自体のパフォーマンスが高くてもトラフィックが詰まると使い勝手が悪くなってしまうため、Copilot+ PCをはじめとしたAI PCのパフォーマンスを十分に引き出すためには、Wi-Fi 7対応のアクセスポイントへのリプレースが不可欠となるでしょう。またこのWi-Fi 7アクセスポイントを最大限に活用するためには給電方式の見直しも求められるため、スイッチやルーターなどのモダナイゼーションも求められます」と語る。
通信の快適性を担保するためには、ネットワーク障害をいち早く察知し、その原因を特定して解決することも必要だ。シスコシステムズは2020年にThousandEyesを買収し、エンドツーエンドにおけるトラフィックのパフォーマンスを常時測定する「ThousandEyes プラットフォーム」を展開している。このプラットフォームはネットワークパフォーマンスの常時監視に加えて、複雑なトラブルシューティングをスムーズに行える。シスコシステムズではこのThousandEyes プラットフォームの機能を、同社の「Cisco Meraki」(以下、Meraki)や「Cisco Catalyst」(以下、Catalyst)へ組み込みながら、ラインアップの見直しも進めている。
シスコシステムズ ネットワーキング事業 SE本部長 高田和夫氏は「当社ではこれまでMerakiと呼ばれるクラウドベースの管理プラットフォームと、Catalystシリーズと呼ばれるオンプレミスベースの管理プラットフォームを展開していました。今後はこれらのシリーズのハードウェアの統一化を進めていきます。現在でもMerakiのクラウド管理体験とCatalystの高性能スイッチングの統合を進めており、お客さまの管理環境がクラウドでもオンプレミスでもハイブリッドでも、Wi-Fi7対応のアクセスポイントを含むネットワークをスムーズに運用可能です。マルチモーダル対応のAI PCの普及に伴い、ネットワークのミッションクリティカル性が高まる中、ThousandEyesの監視機能がMerakiダッシュボードおよびCatalyst管理プラットフォームと連携し、ネットワークのトラブルシューティングや可視化がより効果的に行えます」と語る。

執行役員
ネットワーキング事業担当
高橋 敦 氏

ネットワーキング事業
プリンシパルソリューションズエンジニア
生田和正 氏

ネットワーキング事業
SE本部長
高田和夫 氏

セキュリティ事業
SE本部長
中村光宏 氏
三つのステップで
AIアプリのリスクを防げ
AI技術の台頭によって大きなテクノロジーシフトが起こっている。シスコシステムズもその変化に対応すべく、2025年6月にサンディエゴで開催された同社主催のITイベントである「Cisco Live」において、エージェンティックAIへの移行を支援する幅広い新製品や機能強化を発表している。その中で特に注目されたのが「Cisco AI Canvas」だ。Cisco AI Canvasは、AIを活用したネットワークのトラブルシューティングが行える機能で、IT管理者は自然言語インターフェースを用いて会話するようにネットワーク周りのトラブル解決が図れる。
シスコシステムズ セキュリティ事業 SE本部長 中村光宏氏は「AI PC運用の上では、セキュリティの観点も重視する必要があるでしょう。AIに潜むリスクに対して、当社ではAIセキュリティソリューション『Cisco AI Defense』を提案しており、AIアプリケーションに潜むリスクを『発見』『検出』『保護』という三つのステップで防御します。LLMは回答精度を上げるためにファインチューニングが行われますが、これによって安全性が下がるというリスクもあります。そういったリスクをCisco AI Defenseによってチェックし、いわゆる『ガードレール』によってさまざまなAIモデルをセキュアに運用できるようにしていくことも必要です」と指摘した。
最後に高橋氏は「Copilot+ PCをはじめとしたAI PCへのリプレースは、ネットワークのモダナイゼーションを進める上でも良いタイミングになるでしょう。ネットワークのモダナイゼーションはその企業の競争力を高める上でも非常に重要になります。またネットワークのことだけでなくセキュリティも組み合わせて検討することが非常に重要になりますので、ディストリビューターやパートナーの皆さまと共に提案を進めていきたいと思います」と締めくくった。