経済同友会がAI活用促進に向けて提言
企業にコア業務でのAI活用と内製化を求める
経済同友会は2025年4月4日、AI活用に関する提言「不確実性とAI〜進化と適応の新時代へ〜」を発表した。提言ではAIが急速に進化してビジネスや社会にどのような変化を引き起こすのかが予測できない不確実な環境の中で、企業、政府、個人のそれぞれに対して対応能力を引き上げるために取るべき行動が示されている。
経済同友会がAI活用促進に向けた提言
2025年4月4日、経済同友会はAI活用に関する提言を発表した。提言では不確実な環境の中で、企業、政府、個人のそれぞれに対して対応能力を引き上げるための取るべき行動が示されている。その内容と説明会の様子をリポートする。

日本はAI活用が後れているが
まだ変革の好機を生かせる
「不確実性とAI〜進化と適応の新時代へ〜」はAIの進化と普及によってもたらされる不確実な環境の変化に対応するための企業、政府、個人がそれぞれ取るべき行動を示した提言であるが、これはAIを効果的に活用するための指針とも捉えることができる。
この提言を作成したのは経済同友会の「企業のDX推進委員会」で、デジタルガレージ 取締役および千葉工業大学 学長を務める伊藤穰一氏とPKSHA Technologyの代表取締役を務める上野山勝也氏、そしてインテルの取締役会長を今年3月末まで務めた鈴木国正氏の3名の同委員会委員長らが提言の発表および説明を行った。
提言を検討した背景と理由について上野山氏は次のように説明した。まず日常会話で用いられている「言葉」を使ってAIと会話ができるようになり、テクノロジーと生活者の関係が劇的に変わる可能性が生じていること、持続的な賃上げ、金利のある世界の回帰などの変化から経済成長のエンジンが動き出す中で、その発展の足かせとなる深刻な人手不足・人材不足の常態化の解決策としてAIの活用が必須になっていること、しかし日本では生成AIの活用が海外と比較して後れており、過去にもインターネットやクラウド導入、DX推進でも後れを取るなど、テクノロジーを活用した企業戦略および戦術を基に企業価値を上げることができなかった反省があるという3点を挙げた。
しかしAIの技術はまだまだ黎明期であり、ソフトウェアがAIに変わっていく大きなトレンドが動き出したばかりであるため、今ならが後れを挽回して変革の好機を生かせると強調した。


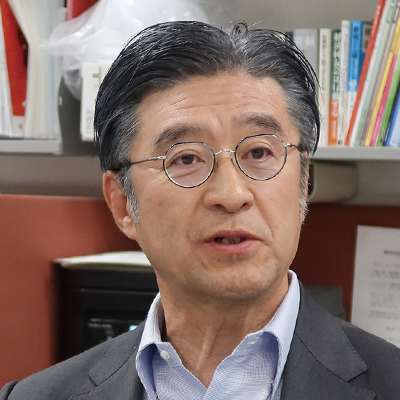
日本の強みは「おもてなし・和み」
AIoT、半導体、テクノロジーとの共存
そしてAI活用において日本の強を生かした四つの取り組みを挙げた。一つ目はAIアプリケーションに「おもてなし・和み」や職人気質の精神といった日本人独自の本質的価値を組み込む独創的なアプローチを取ること。二つ目はAI of Things(AIoT)としての日本のデバイス構築能力を生かして製造技術とインフラを融合させ、高品質なIoTデバイスと通信技術を用いたスマートファクトリーやスマート家電で市場拡大を図ること。
三つ目は半導体グローバルバリューチェーンにおいて半導体素材や製造装置の国際的な日本の強みの発揮と、複数チップを統合する先端パッケージにおけるウェハーの後工程における製造受託企業との連携強化による日本独自の競争優位の確立、そして四つ目はドラえもんや鉄腕アトムといったテクノロジーの共存に肯定的な日本人の意識を生かして人手不足解消にAIを積極的に活用していくことだ。
これらをまとめて上野山氏は「日本人ならではのAIの向き合い方を創り、米欧諸国との差別化やアジアと文化を共有する国としてグローバルの中で独自のポジショニングを形成していくことが重要です」とまとめた。
AI活用に関する提言
「不確実性とAI〜進化と適応の新時代へ〜」の概要
【1】企業への提言
1.「ノンコア業務」だけでなく「コア業務」へAIを活用し競争力強化
AI導入の最大の効果は主たる事業の本丸に使うことで、事業価値の最大化が実現
2. CAIOを設置し、ソフトウェア・AI設計の外部依存モデルを早期脱却
技術速度が速く、事業範囲が広い、かつリスク管理が重要なため、専門的責任者(CAIO)が必要
3. ソフトウェア・AI活用が評価・推進する人事制度・人材育成の仕組みへ変革
デジタル時代に対応するためには新たな評価基準が必要、人事制度・人材育成の変革
4. AI活用のガバナンス・ルールの設定・更新
ガバナンスにおける二重のループを更新し続けること、さらにサイバーセキュリティが重要
【2】政府への提言
1. AI・半導体・エネルギーの3分野での横断連携の強化
「AIをそもそも何に使うべきか」を考え、五つのレイヤーを俯瞰して戦略に落とし込むことが必要
2. 日本の強みを生かすAIoT領域への産業投資の促進
日本の強みを生かすAIoT領域への産業投資を促進、AI Embedded Machine領域へ重点的に投資を加速
3. AIの利活用促進のためのデータ活用・個人情報保護法へのアップデート
データ利活用による社会課題の解決が重要な課題になる中で個人情報保護法のアップデートが必要
4. DFFTの流れを、データネットワーク構造立ち上げに接続させる
DFFTの流れを、データネットワーク構造立ち上げに接続させ、データと産業を連携
5. デジタルやAIリテラシーヘのさらなる強化
産業や教育界ではさまざまなベストプラクティスを基に、人材政策を点から線、線から面への活動
【3】個人への提言
1. 好奇心と批判思考の重要度が高まる
好奇心や批判思考を養う必要、AI時代は「問題を解く力」よりも「問題を設定する力」が重要
2. AIに何を任せ、何を任せないか
AIをツールと考え、苦手な部分をAIに任せることで、個人の能力や才能を拡張
ノンコア業務だけではなく
コア業務にもAI活用を推進
この日に発表された提言は企業、政府、個人の三つの視点でAIによる不確実環境下への対応能力を上げて、AI活用による変革の好機を生かすために取るべき行動が示されている。
まず企業へのAIを活用した競争力強化への取り組みについて、「ノンコア業務だけではなくコア業務にもAI活用を推進して競争力の強化を図ること」「AIについて取り組みの責任の中心を担うCAIO(Chief AI Officer:最高AI責任者)を設置して、ソフトウェア設計およびAI設計の外部依存モデルを早期に脱却すること」「ソフトウェアおよびAIを活用するスキルや推進する役割を評価する人事制度・人材育成の仕組みを導入すること」「AI活用のガバナンスとルールの設定・更新をすること」の四つを提言した。
デジタル化への取り組みが進まない日本の中小企業では、AI活用がもたらす生産性向上が人手不足・人材不足を補う効果が期待できる一方でAI活用に伴うコスト負担や人材不足が足かせとなり、AI活用を促進するには中小企業に特化した考え方や進め方が必要なのではないかとの質問に対して、鈴木氏は「まずは大企業からAI活用による競争力強化を図っていき、その効果が中小企業に波及していくよう別の取り組みが必要だということは認識しています」と説明した。
政府への提言については「AI・半導体・エネルギーの3分野での横断連携の強化」「日本の強みを生かすAIoT領域への産業投資の促進」「AIの利活用促進のためのデータ活用・個人情報保護法へのアップデート」「日本が提唱するDFFT(Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)の流れをデータネットワーク構造立ち上げに接続させる」「デジタルやAIリテラシーヘのさらなる強化」の五つ、そして個人に対しては「好奇心と批判思考の重要度の高まり」と「AIに何を任せ、何を任せないか」の二つを提言した。


